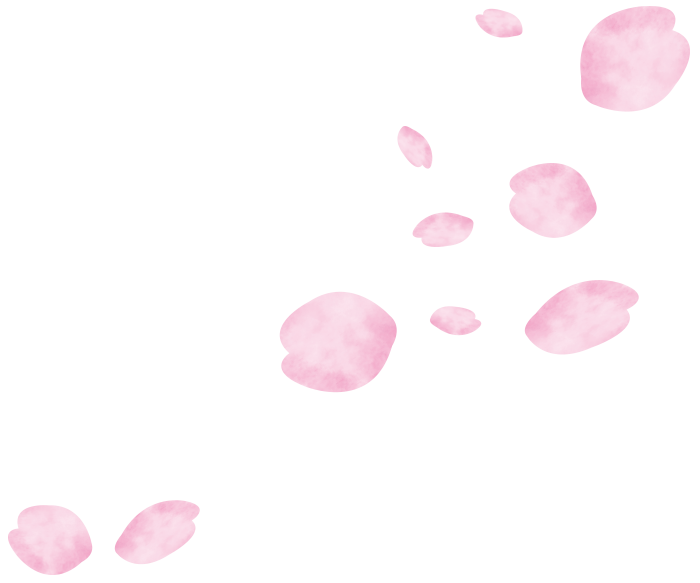
日本舞踊はすなわち日本の踊りです。
日本の踊りといってもあくまでも舞台上で上演する事を目的とした一個の舞台芸術です。
「日本舞踊」は能から伝わる「舞(まい)」と、歌舞伎からでた「踊(おどり)」という2種類の動きがあります。「舞」はゆったりした「すり足」、テンポ早く舞台の上を回る動きなど、比較的単純な動作を組み合わせ繰り返します。
一方、歌舞伎から生まれた「踊」は華やかで活発な動きが多く、足を上げたり、回ったりと様々な振りがあります。
使われる音楽の基本は三味線で、そこに唄や語りを組み合わせて情景や物語を作り出し、その場面にあった衣装、振り付けで登場人物の心を表現します。



紅を売り歩く女の姿を描いたもので、恋心を淡く切なくしっとりと唄っている演目です。
紅を使う女の人の心情を踊り分け、再び次の街に向けて過ぎてゆく、そんな風景を表現するような踊りです。
手習子とは、寺子屋に通う子供のことを指します。
帰り道に道草をしながら、草紙を持って蝶を捕まえようとしたり、手習いのお師匠さんへの淡い恋心を打ち明けてみたりと、幼い少女が可愛らしい仕帰草で春の野辺に遊ぶ様子を描いた曲です。